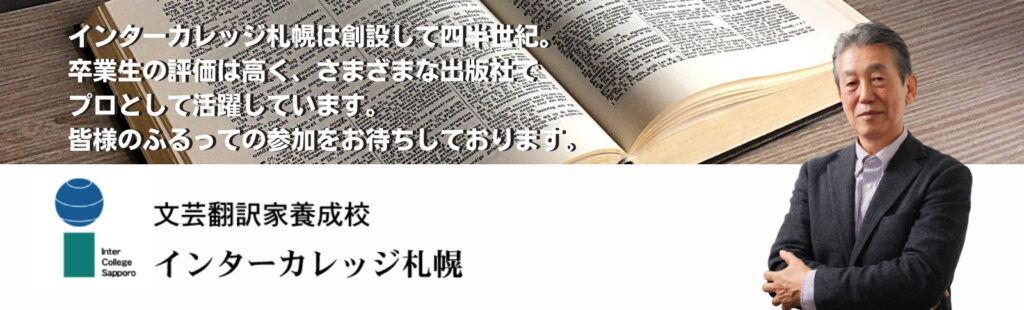僕が翻訳家になるまで ②
さてその“翻訳”のほうですが、僕にはどうしても、翻訳家であることの“罪悪感”みたいなものが付いて離れないのです。どうしてそうなのか、理由ははっきりわかりませんが、僕にはやはり第二次大戦中の生まれであることや、十代の若さでアメリカ生活を一年送ったことなどが原因となっている気がしてなりません。
敗戦国日本、そしてその代表の一人としてアメリカへ渡った僕。その一年間で、僕には癒しがたい“負”の臭いが染み付いてしまったのかもしれません。帰国後も外国人とはしょっちゅう会っていたし、友達も沢山出来ました。しかし僕にはやはり、残念ながら、“負けた人間”という自分でも予期せぬイメージが付きまとっているようなのです。
そしてその負けた国の人間が、勝った国の人間の言葉を駆使して仕事をするというのは、どう考えてもフェアーな関係ではないように思われたのです。強い者の尻拭いをして生きる人間……それがまさに翻訳家ではないか、そんな気がしてなりませんでした。
本来なら僕にうってつけの仕事ではないかもしれない。したがって自分の名刺も作らず、友人にはちょっとバイトをしているんだと言うだけでした。しかしながら、僕はその仕事にのめり込んで行ったのです。
1年に10作品と言えば、ほとんど不可能な感じです。700ページの中篇を2週間でやり遂げたこともあります。1日10ページが平均ですから、約5倍の速さになります。結局は、翻訳家という作業は自分に向いてないと言う思いが、作品を“事務的”に取り扱うという良い結果をもたらしたのではないでしょうか。
かつて、どこかの出版社が各翻訳家の一年間の仕事量を表に出していたことがあります。自慢にもなりませんが、僕は20年ほど、つねにそのトップか2, 3位にいたものです。今にして思えば不思議な話ですよね。翻訳家なんてくそ食らえと思っていた僕が、そんな調子だったのですから。
しかしこれは、僕が己を知らないということなのかもしれません。もしきちんと自己判断ができるのなら、僕は翻訳家が向いていると気づくはずなのです。しかしそこに、剣道があった。僕としては何にもかえることができないものです。そしてその剣道があったからこそ、僕は、翻訳業にも“真面目”に向き合うことができたように思うのです。