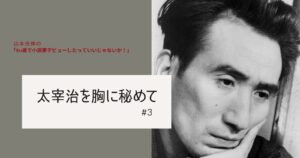三島由紀夫の嘆きについて考える ⑥
さらに言えば、こんなこともありました。東京の女性(女房の友人です)から突然、札幌の僕の所へ電話が入り、100万を貸して欲しいというのです。女房や息子たちはまだ逗子にいました。そこで僕は出版社から100 万を借り、彼女に振り込みました。問題は本来それだけで終わるのですが、三年ほどして彼女の話が話題になり、僕はうっかりと、そう言えば彼女にお金を貸したっけ、と話してしまったのです。
さあて、それを聞いて女房がきっとなりました。何と女房もその時、彼女に100万を貸していたのです! 計200万。女房は、彼女がそういう類の女性であることを知っている上で貸したのだそうです。で、僕はどうしたか? 「いやあ、彼女もやるねえ!」の一言でチョンとなりました。ウソー、の声が聞こえてきそうですが、僕は貸した瞬間から忘れてしまうのでそういうことになるのです。これはもう若い頃からの習性でそうなるので、それが果たしていいことなのかも実ははっきりしないのです。
僕はたぶん、現実の世界で生きるには判断が甘すぎるのでしょう。だからこその現在の難行苦行があるのでしょう。それでもなお、僕は金貸しが威張るような、金融関係者が幅を利かすような世の中にはなってもらいたくありません。どうしてお金を貸すと人はふんぞり返るのか、僕にはどうしても理解できないのです。
投資会社を経営する僕の友人(彼もまた親友でした)が、人間にとってお金は命の次に大切なものだ、と言ったことがあります。すかさず僕は反論しました。そんなことを言ってるから、日本の文化はいつまでたっても“四畳半芸術”の域を出られないんだ、と。ベンチャービジネスがいつも中途半端に終わるのもそのせいなのだ、と。みなさんはどう考えられますか?