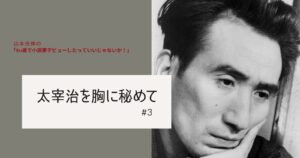伊藤整文学賞の断絶について
私は言いようのない寂寥感を覚えざるを得ない。直木賞や芥川賞に並んで、いやそれらよりも実質的な重みのある文学賞だと思っていただけに、なお更だ。
運営委員の皆様には、これまでの多大の努力に感謝を申し上げたい。おそらく口には出せないご苦労がいろいろあったことだろう。しかしながら、新聞紙上で見るかぎり、残念だが仕方がない、という「廃止ありき」の論調で終始しているのが気になった。
新聞によれば、廃止止むなしの大きな理由は、資金不足と運営委員の高齢化だという。そのニュースを読んで、私は本当だろうか、と思った。本当に、たかだかそんな理由で伊藤整文学賞をつぶすつもりなのか。皆の目がさまざまな“東京の賞”に集中しているなかで、地方都市小樽で燦然と輝いているのが伊藤整文学賞ではなかったのか。それこそまさに、「北に一星あり。小なりといえど、その光輝強し」なのだ。

高齢化が理由ならば、人事刷新を図ればいい。このような問題は突然に降って湧くものではなく、したがって、これまでに対抗策を講じてこなかった運営委員会側の怠慢ということになる。まさか、若い世代に運営委員の引き受けてがいないというわけではないだろう。
また、年間の運営経費は五百万円ほどだという。確かに大きな金額だが、500人が年会費1万円を支払えば済むことだろう。小樽を活動の場にしている数多の企業は何をしているのか。高校や大学の関係者はどう考えているのか。各大学のOB会は我関せずを決め込んでいるのか。
私は会う人ごとに、とりわけ小樽に関わりのある方々に、今回の件をどう思うか尋ねてみた。百人が百人とも、伊藤整文学賞の存続に賛成で、しかも何らかの形で協力したいということだった。それなのになぜ、残念だが仕方がない、ということになってしまうのか。
これこそ、故郷への恩返しというものだろう。人生の一時期、とりわけ多感な青春時代を過ごした土地こそが故郷と呼ぶにふさわしい。まずは心ある小樽市民に声を上げていただきたい。市民の熱い想いが不可欠なのだ。行政側はその声と想いに真摯に耳を傾けなければなるまい。
文化に無関心な個人、社会、都市はいずれ衰退する。そう私は頑なに信じている。経済活動であれなんであれ、人間の営みを底で支えているのは常に文化(精神)なのだ。本を忘れて末に走り、目先の損得にかかずらっているようでは話にならない。景気が低迷している今こそ、その事実をみんなが肝に銘じる絶好の機会ではないか。
小樽市民だけではない。全道民が力を合わせ、あの日本に誇る伊藤整文学賞を復活、いや存続させようではないか。
(2014年執筆のブログより)