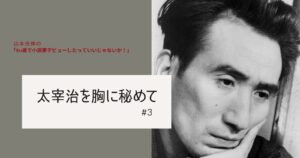母の思い出
僕には“母”の思い出があります。ウチは父が職業軍人だったため終戦後は一転して貧しい人生を送りました。父は36歳、海軍中佐で終戦を迎えました。自衛隊からの熱心な誘いを断り、彼は協和発酵に勤めて一従業員として人生を終えたのでした。
したがって終戦後の我が家はきわめて貧しかったようです。僕も高校三年までの間に、買ってもらったのはレインコート一着だったことを覚えています。もちろんそんなことはないわけですが、僕にはそのように記憶されているのです。
さて、場所は吉祥寺です。僕は6歳まで吉祥寺にいて、それから皆で逗子に移ったのです。年齢はたぶん5歳くらいでなかったかと思います。僕は近所で遊んでいて、地面に花が咲いているのを見つけたのです。その小さな花は、地面一杯に咲いていました。僕は夢中で地面に這い蹲り、その花を腕一杯に毟り取りました。
そしてそれをいそいそと自宅まで運び、母親に差し出したのです。「花だよ、母ちゃん!」とたぶんそう言ったのでしょう。母はびっくりしてそれを受け取ったものの、声を低くしてこう言ったのです。「光伸、これはお百姓さんの食べ物ですよ」と。ただし、残念ながらこの言葉はまったく覚えていません。
それから僕は母に手を引かれて、その“花”を返しに行きました。と言うよりも、新芽を息子が盗んだことを謝りに行ったのでしょう。謝りに行って、相手が何と答えたかは記憶にない。その帰り道のことです。
母は僕を一切叱らず、背中に負ぶってくれました。歩く先に夕日が落ち、母と僕は金色に染め抜かれました。僕かこの年になってもはっきりと覚えているのは、その太陽光です。ギラギラと照りつける太陽光。当時、生活苦に喘ぎながら日々を過ごすことでいっぱいだった母にとって、それが何かの記憶として止まっているかどうかはわかりません。僕は母に負んぶされ全身に陽光を浴びながら、母の背中にしっかりと抱きついていたのでした。
僕が子供の頃に覚えている母親の姿はそれだけです。しかしその姿は、何やら僕が年を取るに連れて鮮明になってゆくようなのです。取るに足りない話でありながら、当人にとっては宝物にも勝るもの。そういったものが多くの方の胸の中にも一つや二つはあるでしょう。僕にとっては、それこそが宝物なのです。僕は今日もなお、時折この昔語を思い出しては、98歳で北海道で亡くなった母のことを懐かしんでいます。お母さん、ありがとう!